
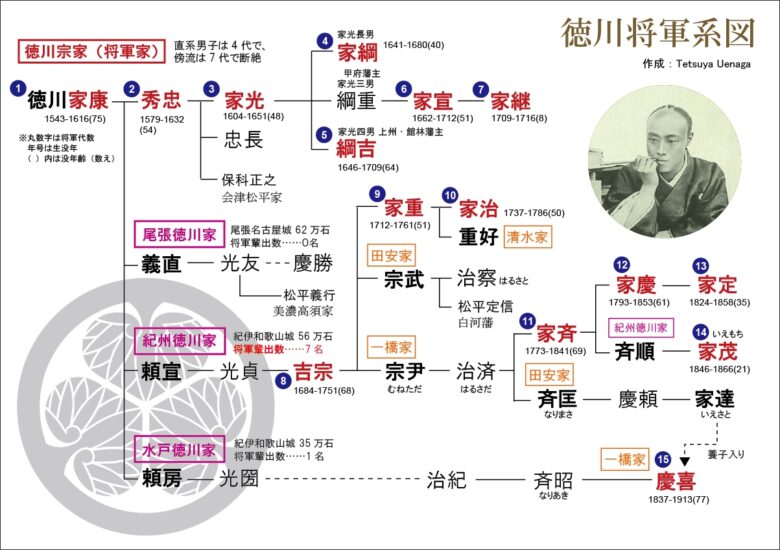
参勤交代
ざっくりいうと、江戸幕府が全国の大名に対して、江戸と領地(藩)を1年交代で往復させ、一定期間江戸に居住させた制度。
江戸時代の大名屋敷

今回行くところ
- 常盤橋公園
- 常盤橋門は、1629年(寛永6年)に出羽・陸奥の大名によって築造されました。門は、江戸城諸門の中でも奥州道中につながる江戸五口(田安門、半蔵門、外桜田門、常盤橋門、神田橋門)の一つで、浅草口、追手(大手)口とも呼ばれました。江戸城内郭の正門である大手門に接続することから、軍事上重要な門に位置付けられました。
- 門の構造は、内桝形門形式の桝形門で、北側に渡櫓とそれを支える石垣があり、門をくぐった先には大番所が配置されました。
- 越前福井藩邸跡
- 画像1
- 画像2
- 江戸時代、この辺りには福井藩の常盤橋上屋敷(藩邸)がありました。福井藩・越前松平家の藩祖は、徳川家康の次男結城秀康で、二代目から松平の姓となり、親藩大名として幕末まで続きました。常磐橋上屋敷は、正徳三年(一七一三)に藩主松平吉邦が拝領し、七三〇〇坪余(二万四千平方メートル余)の広さで、江戸城に近く、江戸屋敷(上・中・下屋敷)の中でも最も重要であり、藩主とその家族の居宅として使われました。幕末に活躍した藩主松平春嶽(慶永)や家臣の橋本左内なども、ここを拠点に活動しました。この地に江戸時代から平成の世へと至る「時をつなぐ」象徴として、福井藩ゆかりのタカオモミジ(福井県福井市足羽神社)とウコンザクラ(福井県敦賀市西福寺)を植えるものです。
- 道三橋跡
- 画像
- 1590年(天正18年)に徳川家康が江戸に入国し、江戸城建設の物資補給路のために竜の口(和田倉門のそば)から銭瓶橋(ぜにがめばし)まで掘割を開削させ、道三掘と呼びました。そのほぼ中間点、現在の丸の内一丁目と大手町一丁目の境に架けられていたのが道三橋です。慶長年間(1596年~1614年)には堀に沿って材木屋等の町屋が立ち並びましたが、その後武家地となり、大名家が屋敷を構えました。当初は大橋と呼ばれていましたが、南東の端に幕府典薬寮(てんやくりょう)の医官今大路(いまおおじ)道三(どうさん)の屋敷があったことから道三橋と呼ばれるようになりました。また、橋の西側に熊本藩(現在の熊本県)細川家の屋敷があり、当主の代々の幼名が彦次郎であったことから彦次郎橋とも呼ばれていました。1909年(明治42年)、道三堀が埋め立てられ橋も姿を消しました。
- 福井藩上屋敷(龍ノ口)跡
- 画像
- 寛永十年(一六三三)に江戸城本丸大手門の前に建てられた越前福井藩主・松平忠昌(まつだいらただまさ)の上屋敷跡です。 広大な敷地に桃山風の豪壮な建物が建っていましたが、明暦の大火により焼失し、以後このような華麗な大名屋敷は姿を消しました。「伊予殿屋敷指図」や「江戸図屏風」などにより、当時の建物の様子がわかっており、江戸東京博物館に復元模型が展示されています。
- 大手門
- 江戸城本丸登城の正門で、城門警護は10万石以上の譜代大名が務めていました。門の建設は1606年(慶長11年)に藤堂高虎が行ったとされ、1657年(明暦3年)明暦の大火で焼失した後1659年(万治2年)に再建されました。
- 現在の門は、手前の高麗門が1659年、渡櫓門は1966年(昭和41年)に再建された建築物です。門内には、「明暦三丁酉」の記銘がある旧大手門渡櫓の鯱が置かれています。
- 同心番所
登城する大名の供(お供の者)の監視や、通行者の検問を行った下級武士(同心)の詰所 - 大手三之門跡
皇居東御苑の正門(大手門)をくぐり、三の丸から二の丸へ入るための重要な検問門。石垣が残る - 百人番所
大手三之門と中之門の間にある、江戸城最大の番所。伊賀組・甲賀組など鉄砲百人組が昼夜警備に当たったため、この名がついた。 - 中之門跡
本丸へ通じる大手道に設けられた厳重な警備門。大きな石垣が特徴で、この門の内側に大番所が置かれていた - 大番所
中之門の内部に設けられた本丸への最終検問所。他の番所より格上の武士が警備を担当した - 中雀門跡
本丸御殿の正面玄関につながる門で、本丸域への最後の関門。格式が高く、御三家さえも手前で乗物を降りる必要があった - 富士見櫓
本丸の南端に位置する唯一現存する三重櫓。明暦の大火で天守が焼失した後、代用の天守としても利用され、将軍が遠方を望む場所でもあった - 江戸城天守復元模型
江戸城天守があったころの説明展示と模型がある - 江戸城天守台
上る途中に本丸がびっしり屋敷で埋まっているイメージ図は必見!当時の再現模型(画像)

