
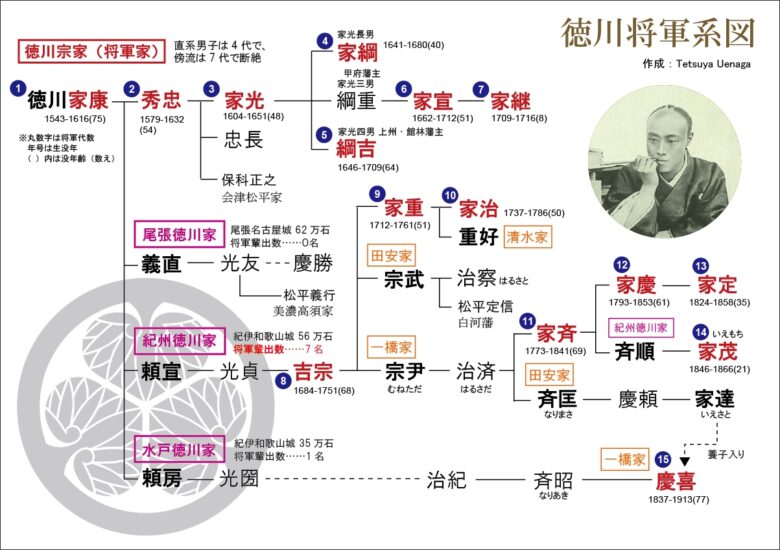
板橋について
現在の板橋区域には、「板橋宿」以外にも中世・近世からの歴史を伝えるものが多くあり、現在の街づくりの基礎や特徴となっているほか、地名などに、その歴史を残すものも見られる。
鎌倉時代末期の『延慶本平家物語』に、1180(治承4)年、源頼朝が「武蔵国豊島ノ上滝野川ノ板橋」に布陣したことが著されていることから、「板橋」の地名は、平安時代、遅くとも鎌倉時代にはあった。地名の由来は「石神井(しゃくじい)川」に架けられていた小橋ともいわれる。江戸期になると「板橋宿」となり、多くの旅人や江戸庶民が訪れる賑わいの地となり、地域の中心地となった。1889(明治22)年の「町村制」施行により「板橋町」となり、1932(昭和7)年に東京市へ編入されると区名にも採用され、「板橋区」が誕生した。
江戸期に賑わった「板橋宿」一帯は、明治期以降も地域の中心地として栄え、1878(明治11)年には「北豊島郡役所」も置かれた。1932(昭和7)年、東京市の拡大により、板橋町、上板橋村、志村、赤塚村、および現在の練馬区域が東京市へ編入され、「板橋区」が誕生、区役所は旧・板橋町に置かれた。1885(明治18)年、日本鉄道品川線(赤羽・品川間)が開通、中間駅として、板橋、新宿、渋谷の3駅(当初は停車場と呼ばれた)が開業した。
「板橋宿」は江戸期には「飯盛旅籠」などで賑わう遊興の地で、明治期に入っても引き続き賑わっていたが、1883(明治16)年に「日本鉄道」(現・JR高崎線)が開業したことで街道の往来は期待できなくなり、さらに翌1884(明治17)年の「板橋大火」で「上宿」「仲宿」を中心に約300軒を焼失したことで、「板橋宿」は大きな打撃を受けた。
1885(明治18)年、「平尾宿」東端付近に「板橋停車場」が開業し、1886(明治19)年には「平尾宿」へ「北豊島郡役所」が移転するなど中心地が南へ移ると、旅籠業者も駅寄りとなる郡役所周辺に移転し再建を図り、遊興客相手の宿・店として営業を開始、「板橋遊廓」へと発展した。
三井住友トラスト不動産「東京都板橋」
https://smtrc.jp/town-archives/city/itabashi/index.html
今回訪れるところ
※各リンクはGoogle Map

