
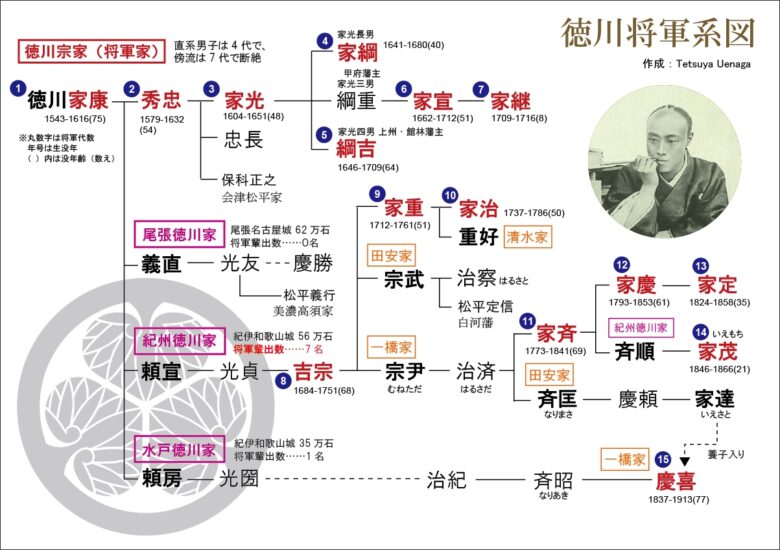
学習院大学目白キャンパス
- 1つのキャンパスしか設置していないが「目白キャンパス」という名称がついている。学習院女子大学は「戸山キャンパス」と呼ばれる。
- 近隣の川村学園キャンパスと豊島区立目白小学校校地と豊島区立千登世橋中学校は旧制時代は学習院の敷地だったが、戦後、売却、譲渡された。
- キャンパス内には豊島区内で唯一の自然林が残存しており、タヌキ・テン・ハクビシン・アオダイショウなどの野生動物が林の中などに生息し、目撃されている。
- 1945年4月の東京大空襲で正堂・本館など木造校舎の大部分が焼け落ちたが、今回行くところの国の登録有形文化財(建造物)はいずれも焼失を免れ、一部改築・改装・移築を経ながら現在まで維持されてきたもの。
- 大学のマスコットキャラクターはさくまサン(公式ページ)
学習院の略歴
- 1847年(弘化4年)、仁孝(にんこう)天皇が京都御所内に設けた公家を対象とした教育機関である「学習所」を開設。
- 1849年(嘉永2年)、京都学習院となる。
- 1876年(明治9年)、明治維新を経て、華族制度が整備されると「華族学校」となる。
- 1877年(明治10年)、改めて学習院と改名された。学習院ではこの年を学校の創立年としている。
- 1884年(明治17年)、宮内省が所轄する正式な官立学校となる。
- 第二次世界大戦前、皇族、華族が優遇されるという待遇格差があったため、華族を中心とした学校として維持してきた(皇族就学令)。
- 第二次世界大戦後、華族制度が廃止されると私立の学校法人学習院として再出発し、待遇格差も無くなった。しかし近年でも一部の皇族が入学し、“御学友”(一般人で同席を許された特別な生徒)が存在するなど、戦前の学習院の痕跡を残している。
行くところ
★は国の登録有形文化財。( )内の数字は建造年。
- JR目白駅
- 学習院正門(1901)★
目白駅前にあるのは西門であるため注意。 - 北別館(史料館)(旧図書館)(1902)★
- 付近に旧中央教室前噴水御影石がある。
- 東別館(旧皇族寮)(1913)★
- 霞会館記念学習院ミュージアム
- 30分くらい?見学
- じっくり見たい人はあとでゆっくり見てよいと思います。
- 西1号館(旧中等科教場)(1930)★
- 中央教室(ピラミッド校舎)頂部
- 北1号館(旧文学部棟)、南2号館、大学図書館とともに前川國男が設計した建造物で、1960年8月に竣工。厳密なピラミッド型ではないが、ピラミッドのような形だったため「ピラ校」と通称され、大学学生証の裏にイラストが使用される等、キャンパスのシンボル的存在であった。
- ピラミッド校舎の画像
- 2008年に解体され、跡地には中央教育研究棟(高さ50.40m)が竣工。2階ホールにはピラミッド校舎の1/100模型が飾られている(入れるか不明)。
- 南1号館(旧理科特別教場)(1927)★
- 乃木館(旧総寮部)(1901)★
- 1907年1月31日、軍事参議官の乃木は学習院長を兼任することとなったが、この人事には明治天皇が大きく関与した。山縣有朋は、時の参謀総長・児玉源太郎の急逝を受け、乃木を後継の参謀総長とする人事案を天皇に内奏したが、天皇はこの人事案に裁可を与えず、皇孫(後の昭和天皇)が学習院に入学することから、その養育を乃木に託すべく、乃木を学習院長に指名した。
- 乃木は当時の学習院の雰囲気を一新するため、全寮制を布き、6棟の寄宿舎を建て、学生と寝食を共にして生活の細部にわたって指導に努めた。その際の乃木の居室であった総寮部は、「乃木館」として現在も保存されている。
- 生徒からの評判(肯定派):乃木は、自宅へは月に1、2回帰宅するが、それ以外の日は学習院中等科および高等科の全生徒と共に寄宿舎に入って寝食を共にした。乃木は、生徒に親しく声をかけ、よく駄洒落を飛ばして生徒を笑わせた。学習院の生徒は乃木を「うちのおやじ」と言い合って敬愛した。
- 生徒からの評判(否定派):同人雑誌『白樺』を軸に「白樺派」を結成し、乃木の教育方針を非文明的であると嘲笑した。
- 付近に乃木大将経営榊壇、榊壇碑・国境採取石塊碑、年代測定室跡 (14C年代測定発祥の地)などがある。
- 御榊壇(おさかきだん)と呼ばれる聖域は1909年に明治天皇の目白校地行幸を永く記念するため、乃木希典院長が1910年3月、周囲に石を巡らし築いた前方後円の壇で、円壇の中央に天覧の榊の木が植えられている。円壇を囲む石の一部は、乃木が当時の日本の東西南北国境から集めたものである。
- 厩舎(1901)★
いつも馬術部員がいて馬の紹介してくれていたので今回もいるかも。開いていれば一声かけて中の見学ができます。 - 富士見茶屋跡
- 付近に無着堂(坐禅堂)、鳩魂碑などがある。
- 血洗いの池
- 元は湧水でできた用水池で、江戸時代には灌漑に使われており、水門・水路があった。学習院の構内になった後、赤穂浪士の1人堀部武庸が「高田馬場の決闘」において叔父の仇を討った血刀をこの池で洗ったという伝説が語られるようになった。
- この伝説は大正時代の学生による創作で全く根拠はなく、史実ではないが、いつしかこの池を「血洗いの池」と呼ぶようになった。
目白文化村
現在の東京都新宿区中落合1丁目と2丁目の一部、3丁目と4丁目の大半、中井2丁目、西落合1丁目一部にかかる一帯の区域に該当する大正時代から昭和時代にかけて存在した、郊外住宅地の名称。1914年に堤康次郎が、東京府落合村下落合の大地主・宇田川家から2667坪を購入。以後、毎年の様に早稲田大学や近衛家・相馬家所有の地所など周辺の土地を入手していった。更に堤自身も下落合に居を構えると共に、堤の経営する箱根土地(後のコクド)や東京護謨(現在の西武ポリマー化成)が事業拠点を移すなど、一体の開発を本格的に始めていった。
行くところ
- JR目白駅
- 近衛篤麿旧居跡の碑【新宿区地域文化財】
- 旧近衛邸大欅【新宿区地域文化財】
- 五摂家筆頭の近衛家の邸宅の車廻しにあったと伝えられ、当時の当主近衛篤麿(1863~1904)が好んだという
- 大正11年(1922)の近衛邸分譲後も地域住民の要望により残された
- 堤康次郎(箱根土地)が経済的に困窮した近衛家からここ下落合の土地を入手(国立イベントで紹介した内容)
- 日本バプテストキリスト教 目白ヶ丘教会
- バプテストはキリスト教プロテスタント最大の教派
- 竣工は1950年(昭和25年) 、設計はフランク・ロイド・ライトの弟子の遠藤新(自由学園明日館の設計者)
- 日立目白クラブ (旧学習院昭和寮)
- 日立目白クラブは、もとは1928年開設の学習院旧制高等科男子生徒用に建てられた寄宿舎「旧学習院昭和寮」。現在は日立グループの社員と家族向けの福利厚生施設・クラブハウスとして懇親会や結婚式の披露宴などに利用されている。
- イギリスのイートン校の寄宿舎を模範にした
- おとめ山公園【下の池】※適当に散策でOK
おとめ山公園は落合崖線に残された斜面緑地です。江戸時代、おとめ山公園の敷地周辺は、将軍家の鷹狩や猪狩などの狩猟場でした。一帯を立ち入り禁止として「おとめ山(御留山、御禁止山)」と呼ばれ、現在の公園の名称の由来となっています。大正期に入り、相馬家が広大な庭園をもつ屋敷を造成しました。のちに売却され、森林の喪失を憂えた地元の人たちが「落合の秘境」を保存する運動を起こし、昭和44年(1969)にその一部が公園として開園しました。 - おとめ山公園【上の池・中の池】※適当に散策でOK
- 中村彝アトリエ記念館
- 中村彝(つね、1887~1924)は茨城県水戸出身の洋画家
- 入館無料。滞在は15~20分くらい?長居しないように注意
- 日本聖公会東京教区目白聖公会
- 東京にある聖公会の中で唯一の戦前からある教会
- 1929年、現在のロマネスク様式の聖堂が建造された
- 公益財団法人 徳川黎明会
- 尾張徳川家19代当主、徳川義親の邸宅跡。
- 1932年(昭和7年)竣工。設計は国立博物館本館や第一生命館、銀座和光を手がけた渡辺仁
- このエリアに徳川ビレッジといわれる外国人用高級賃貸住宅がある
- 豊島区立 目白庭園
大野家という大地主の邸宅跡地だが、1990年に作庭、開園された歴史の浅い庭園。作庭者は伊藤邦衛(1924~2016)。 - 豊島区立上り屋敷公園
上り屋敷(あがりやしき)は江戸時代の狩猟地における休憩所。この地域の南側(豊島区目白・新宿区下落合)に広がる徳川家の狩猟地に来た将軍らのための休憩所があったことからこの地域の地名となった。現在は地名では残っていないがこの公園にその名前が残る。おとめ山公園とも関連。 - 自由学園明日館(時間あれば)
- 国指定重要文化財(建造物)。1921 年に建築家のフランク・ロイド・ライトの弟子の遠藤新が学校として建てた。現役の学校としては東久留米市学園町に自由学園(幼・小・中・高・大)がある。
- 入館しませんがここで終了なので入りたい人は入ってもよいと思います
- 最寄り駅は池袋駅
江古田・沼袋原の古戦場跡と百観音明治寺
江古田・沼袋原の戦い
1477年5月25日
太田道灌 vs 豊島泰経
長尾景春の乱における局地戦の一つ。道灌は各地を転戦して景春方を攻め潰し、文明12年6月(1480年7月頃)に景春の最後の拠点日野城(現・埼玉県秩父市に所在)を落として、乱を平定した。文明14年(1482年)に古河公方との和議が成立して、30年近くに及んだ関東の争乱は終結した。
江古田・沼袋原の古戦場
付近には、この合戦の戦死者を葬ったとされる「豊島塚(としまづか)」が点在していたとされ、一部は現在も名残りを留めている。
- 四ツ塚
- 金井塚
- 稲荷塚
- お経塚👈今回行く
- 古塚👈今回行く
- 丸山塚👈今回行く
- 金塚
- 蛇塚
- 大塚
- 武蔵野稲荷神社古墳
百観音明治寺(めいじでら)
真言宗東寺派の寺院である。山号は、「新浮侘落山」(しんふだらくさん)、院号は「世尊院」。 境内の一部は区に貸与され、百観音公園として開放されている。
百観音献灯会(けんとうえ)」は「世界中の子どもたちが飢えや貧しさや、戦争の恐怖にさらされることなく、どうか幸せになりますように」と願うことをテーマとし、毎年7月の最終日曜に開いている。
境内に建立されている180体余りの石仏観音像には約1000本のろうそくをともし、献灯会護摩祈祷(きとう)法要を行う。ろうそくには500円を求め、利益はユニセフ募金や災害復興支援NPOなどに全額寄付する。インドネシアの伝統音楽「ガムラン」の演奏や舞踊も予定。
行くところ
- 中野沼袋氷川神社
後村上天皇の時代に武蔵国の一の宮である氷川神社から分霊され、祀られたことに由来する。1477年に太田道灌が豊島氏との間の「江古田・沼袋原の戦い」の際に、当神社に陣営を置いたと言われ、その際戦勝を祈願して境内に杉の木を植えたと言われている。 - お経塚
- 古塚(稲荷塚/狐塚)
- 中野区立 丸山塚公園
- 百観音明治寺

