
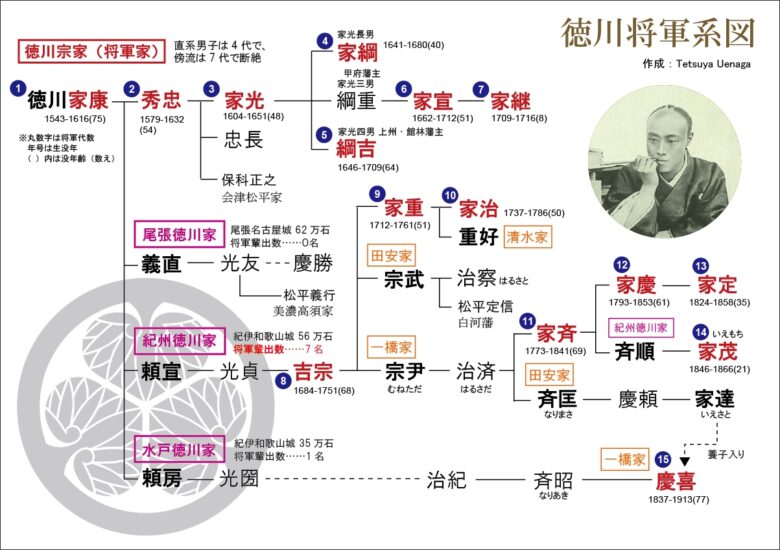
竜閑川とは
竜閑川(りゅうかんがわ)は、東京都中央区および千代田区にかつて存在した河川である。日本橋川より千代田区と中央区の区界に沿って北東に向かい、東神田付近から直角に折れ、浜町川を経て箱崎川、隅田川へと抜ける人工の堀であった。明治の掘割の際に神田川への流路も掘割されている。
明暦の大火(明暦3年、1657年)の後、江戸市中は大規模な防火対策が敷かれ、当地には長さ八丁(約870m)の防火堤防が築かれた。天和3年頃には堤防の周囲が火除地として空いていたが、ここを元禄4年(1691年)に町人たちの負担により、元和年間に引かれていた浜町堀(後の浜町川)と繋ぐ掘割が作られた。神田八丁堀、白銀町堀とも呼ばれ、日本橋と神田の境界になっていた。やがて竜閑川と呼ばれるようになった。
幕末の安政4年(1857年)にいったん埋立てられて消失したが、明治16年(1883年)、東京市の水運の発展とともに堀留として残っていた浜町川を神田川まで延伸(岩井川)させるとともに竜閑川も再び掘割された。
第二次大戦後、ガレキ処理のため昭和23年(1948年)から再び埋立が始まり、昭和25年(1950年)には埋立が完了し、水路としての竜閑川は完全に消滅した。
現在では竜閑川跡は幅1-2mほどの路地となっており、往時の水路の面影はほとんど残っていないが交差点名にその名をいくつか残している。
今回いくところ
以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

